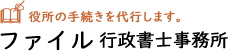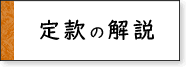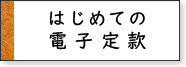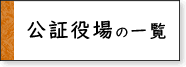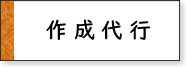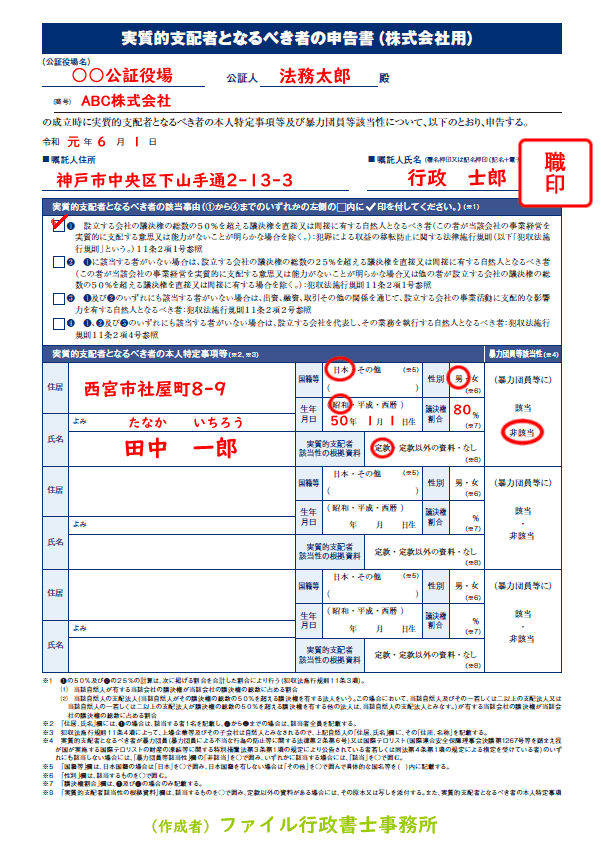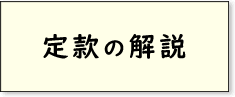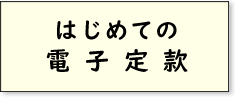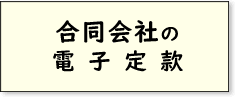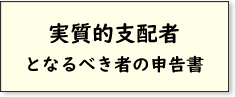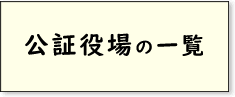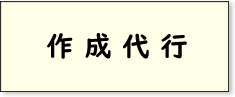実質的支配者となるべき者の申告書
◆ はじめに ◆
2018年11月30日より、
株式会社・一般社団法人・一般財団法人の定款を、
公証役場で認証してもらうのに、
『
実質的支配者となるべき者の申告書』
が必要になりました。
◆ 法的根拠◆
公証人法施行規則 13条の4
犯罪収益移転防止法 4条1項4号
暴力団対策法 2条6号
国際テロリスト財産凍結法 3条1項、4条1項
◆ 趣旨 ◆
法人の実質的支配者を把握することで、
法人の透明性を高め、
マネーロンダリングやテロ資金供与などに、
法人制度が悪用されるのを防止するためのものです。
◆ 対象法人 ◆
・株式会社
・一般社団法人
・一般財団法人
※ 合同会社は、対象ではありません。
◆ 実質的支配者とは? ◆
◆ 定義 ◆
実質的支配者とは、
法人の事業経営を実質的に支配することが可能
となる関係にある個人のことです。
◆ 判断基準 ◆
株式会社の場合、実質的支配者の判断基準は、
簡単にまとめると、次のようです。
(犯罪収益移転防止法施行規則11条2項)
|
実質的支配者の判断基準
|
| (1)議決権の50%超を保有する人 |
| (2)議決権の25%超を保有する人 |
| (3)事業活動に支配的な影響力を有する人 |
| (4)代表取締役 |
上記を、(1)から順番にチェックして、
該当すればその人が実質的支配者です。
◆ 具体例 ◆
発起人田中一郎と田中花子が、株式会社を設立予定。
引受け株数は、以下の場合。
田中一郎 80株
田中花子 20株
まず、
一株一議決権の原則(会社法308条1項本文)により、
次のように、読み替えます。
田中一郎 議決権80個 (80%)
田中花子 議決権20個 (20%)
それから、
(1)議決権50%超の人がいるか、見てみると、
田中一郎が、80%なので該当しますね。
よって、田中一郎が、実質的支配者です。
※ 該当する人がいれば、それ以降の項目はチェックしません。
◆ 記入例 ◆
行政書士が、株式会社の電子定款の作成代行
をする場合の、記入例です。
※ クリックで拡大します
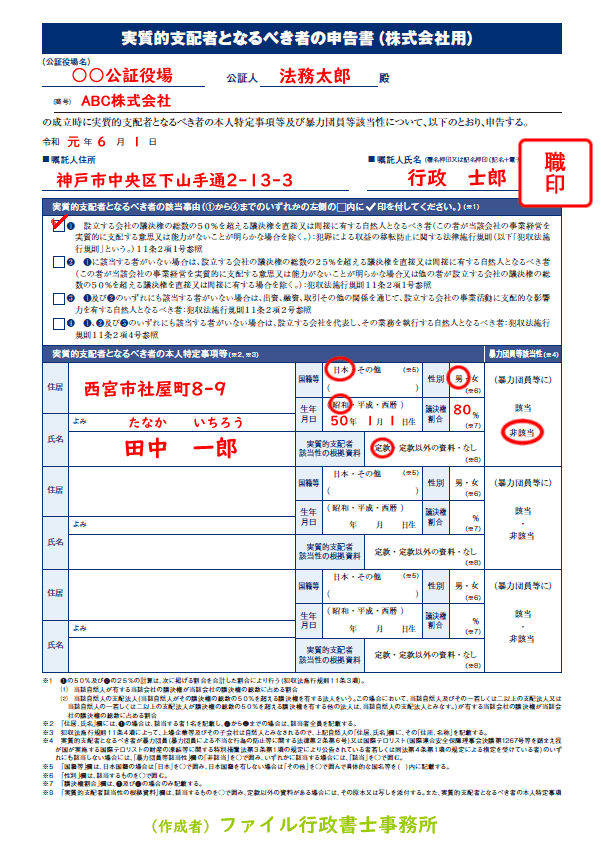
この記入例について、簡単に説明します。
◆ 公証役場名 ◆
ex.
○○公証役場
定款認証してもらう公証役場の名称を書きます。
◆ 公証人名 ◆
ex. 法務太郎
担当される公証人の氏名を書きます。
◆ 商号 ◆
ex. ABC株式会社
設立する会社の名前を書きます。
◆ 年月日 ◆
ex. 令和元年6月1日
申告書の作成日を書きます。
◆ 嘱託人 ◆
ex. 神戸市中央区下山手通2-13-3
行政士郎
ここは、少し分かり難いですね。
まず、『嘱託(しょくたく)人』とは、頼む人という意味です。
そして、公証人に定款認証(会社法30条1項)を頼む人は、
電子定款と紙定款で異なります。
◆ 電子定款の場合 ◆
電子定款に電子署名した人が、
公証人に定款認証して欲しいと頼みます。
(公証人法62条の6第1項2号参照)
なので、電子定款に電子署名した人、
具体的には、
行政書士が、『嘱託人』になります。
これは、実際に公証人に認証してもらった電子定款の認証文
を見てもらえばわかります。
次のようです。
『
嘱託人は、この電磁的記録に記録された情報に
電子署名をしたことを
自認する旨を本職の面前で陳述した。よって、これを認証する。』
◆ 紙定款の場合 ◆
紙定款に署名または記名捺印した人が、
公証人に定款認証して欲しいと頼みます。
(公証人法62条の3第2項参照)
なので、紙定款に署名または記名捺印した人、
具体的には、発起人全員が、『嘱託人』になります。
|
嘱託人
|
|
電子定款
|
電子定款に電子署名した人
(ex. 行政書士)
|
|
紙定款
|
紙定款に署名または記名捺印した人
(ex.発起人全員)
|
◆ 押印 ◆
行政書士の職印を押すか、
または、
電子署名します。
◆ 実質的支配者となるべき者の該当事由 ◆
ex. (1)議決権50%超
実質的支配者の判断基準に、どれを用いたのか。
チェックマークを入れます。
◆ 実質的支配者となるべき者の本人特定事項等 ◆
実質的支配者が複数人いる場合は、
その全員を記載します。
◆住居 ◆
ex. 西宮市社屋町8-9
◆ 氏名 ◆
ex. 田中一郎
(たなかいちろう)
◆ 国籍 ◆
ex. 日本
日本以外の場合は、『その他』に丸印をつけて、
具体的な国名をカッコ内に書きます。
◆ 性別 ◆
ex. 男
◆ 生年月日 ◆
ex. 昭和50年1月1日
◆ 議決権割合 ◆
ex. 80%
議決権割合は、株式数の割合と、考えれば良いです。
(∵一株一議決権の原則)
◆ 実質的支配者該当性の根拠資料 ◆
ex. 定款
『定款』に、各発起人の引受株数が記載されていれば、
定款を根拠資料にできます。
たとえば、次のようです。
第27条 発起人の氏名,住所及び発起人が設立に際して引き受けた株式数は,次のとおりである。
兵庫県神戸市中央区下山手通10丁目9番8号 田中一郎 80株
兵庫県神戸市中央区下山手通10丁目9番8号 田中花子 20株
|
もし、定款に引受株数を記載せず、『発起人の同意書』に記載していれば、
発起人の同意書が根拠資料になります。
暴力団員や国際テロリストに該当するか、しないかを書きます。
◆ 提出方法 ◆
申告書の公証役場への提出方法は、複数あります。
|
提出方法
|
|
・メール送信
|
|
・FAX
|
|
・郵送
|
|
・公証役場へ持参
|
当事務所では、メール送信していますが、
具体的には、次のようです。
(1)申告書をA4の用紙に印刷。
(2)下の実質的支配者に関する欄を、
お客様にご記入いただく。
(3)上の署名欄を、行政書士が記入。
(4)その申告書を、スキャナで、PCに取り込み。
(5)行政書士が電子署名。
(6)公証役場へ、メールで送信。
◆ 提出時期 ◆
この申告書は、早めに提出して欲しいと公証役場から言われます。
定款案をチェックしてもらう段階で、
申告書も送って欲しいと言われたりします。
なので、早めに作成することをお勧めします。
◆ 合同会社は、不要 ◆
合同会社を設立する場合は、
『実質的支配者となるべき者の申告書』は、不要です。
なぜなら、合同会社の定款は、そもそも公証人の認証が不要だからです。
◆ 参考リンク ◆
下記サイトで、パンフレットや書式を、
ダウンロードできます。
● 実質的支配者となるべき者の申告書(日本公証人連合会のHP)
以下は、根拠法令などです。
● 公証人法
● 公証人法施行規則
● 犯罪収益移転防止法
● 暴力団対策法
● 国際テロリスト財産凍結法
次はどのページをご覧になりますか?
|
|
|
|
|
定款の条文を解説。
初心者向け。
|
必要機材と手順を
初心者向けに解説。
|
合同会社は、安いのが
一番のメリット。
|
|
|
|
|
|
※ 現在のページ
|
日本全国の公証役場の
ホームページ・地図。
|
行政書士が作成します。
安心してお任せ下さい。
|